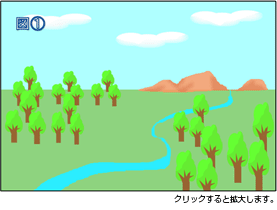 |
|
自然のままの状態の敷地や、耕作地や植林等に使用された敷地も数年間放置されれば、耕作地や植林された敷地であった事を想像する事は困難な状況になります。
これらの状態は、人が家を建てる事を前提とした整地造成が行われなかった為に見られる現象です。
現在は、人工の集中化や整地造成技術の進歩により敷地を使用する利便性の向上の為に、人々が生活する事に適した環境を作り出す事に重きを置いています。
道路や上下水道等の公共設備を中心とした区画整理地業が行われますが、過去の敷地状態が考慮される事は殆どありません。 |
 |
 |
|
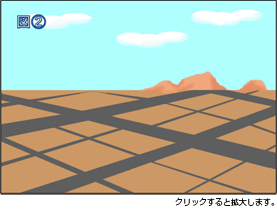 |
|
完成した敷地は人々が住みやすい状況となります。それは敷地の販売に関係した要因も含め、あらゆる側面から生活する為の利便性が高く 付加価値の高い整地造成が行われます。
この状況から、図①の状態を想像することは困難ですし、基本的に、整地造成以前の敷地の付加価値を下げる要因は表だって示されることが少ないと言えます。
さらに近年では、大規模な整地造成が多く 河川の移転や山地の切り崩し、谷地の埋戻し等の造成も大規模で一般に想像される様な 宅地造成のイメージとは大きく異なります。 |
 |
|
|
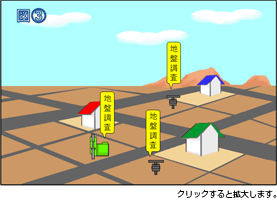 |
|
整地造成が完了し、敷地毎に地盤調査が行われその調査結果に基づき、建物が建築されていきます。その過程で、整地造成が完成した状況から推測しなければ建物の不同沈下の要因を見過ごす事があります。
図2で説明した様に、生活環境や敷地の付加価値の為に整地造成が行われるのであり河川を避けたり、谷地を避けたり、山地の傾斜を生かした整地造成が行われる事は殆どありません。
つまり敷地ごとに、過去の地盤の状況は大きく異なると言うことになります。 |
 |
|
|
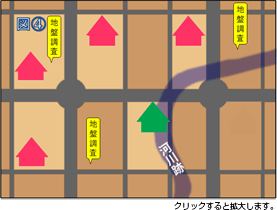 |
|
図2の状態が基本となり、「隣も周辺も問題ないから、自分も大丈夫。」と判断してしまいがちですが、図①の本来の敷地の状況を知る術を持つのは、現地の過去の地盤状況を知る事ができる環境にある近隣の住民や、観測経験のある人に限定されます。
それ以外の場合は、確認する事が出来ない事実が存在する事を重視し、地盤形成や地盤利用状況の視点からも図②の様な地盤状態の敷地がこの場所に造成を行わずに存在する可能性が希少である事に注視し、周辺の調査結果が、該当する敷地と異なる可能性も有ることを理解する事が必要です。該当する敷地の地盤調査データの正確な解析があって初めて成立する地盤への解釈は現実に目視した敷地の状況や、隣地の地盤調査データにより黙殺されてしまう事が有ります。 |
 |
|
|
 |
|
河川の埋戻しや大きな木の堀根等は、図②からは想像する事は困難です。
しかし実際に不同沈下が発生した場合に、過去の地盤状況や造成の経過や現状の敷地状況などを考慮していた場合は、不同沈下を防ぐ事は困難だったと言えるのでしょうか?不同沈下を起こした敷地で、地盤調査を行っており隣接する敷地との調査内容の格差が確認されていて、不同沈下の可能性が検知される地盤調査結果が確認されていたら?この場合、地盤調査の際に何らかの理由より間違ったデータが記録されたのでなければ、隣地とは異なる地盤の堆積状態にあるとデータにより表されます。
建物の安全を確保する為に、それを元に再調査を行うか有効な地盤対策を行う事になります。
つまり、建物の安全を考慮する為には有効な判断材料と成り得る地盤調査が必要でありどんな状況下でも、地盤調査を行わないという事は、不明瞭な危険性を放置する事となります。長期間の建物の安全を確保する為には、地盤に対する明確な根拠が必要とされます。その根拠となりえるのは有効性のある地盤調査だと言えるのでは無いでしょうか? |

