 |
 |
|
|
第1回 擁壁について
第2回 地盤調査について
第3回 盛土の効果とその影響を考える
第4回 地盤の基礎知識
第5回 近日公開予定
| 注意事項 |
地盤シグナルの内容は、地盤総合管理センターが調査した内容を元に編集されています。記述される内容は、地盤総合管理センターの主観であり、特定の敷地や地盤状況を示す物ではありません。また如何なる、設計又は考察の判定に対する影響を考慮した物ではありません。
本文の内容の引用は堅くお断りいたします。
|
|
 |
第1回 擁壁 について
|
 |
【目次】 項目をクリックすると該当部をご覧いただけます。
- <現場観察>は重要な調査項目です
- 小規模建物の不同沈下事故の原因の約80%に関わる<条件>
- <擁壁>の目的と種類
- 擁壁造成された敷地と 建築される建物の関係性
- 擁壁に見られる異常とは
- 擁壁に異常が見られなくても不同沈下は発生します
- 支持力不足の地盤や盛土による造成地盤に設置された擁壁について
- 擁壁のある敷地は擁壁に関係した対策が必要です
- 擁壁が関係した敷地なら 調査・検討は必要です
|
|
 |
|
- <現場観察>は重要な調査項目です
目視で現場を確認し、周辺状況から予定される建物への影響を推測し
地盤調査の考察に活用することが大切です。
目視だけではなく、近隣の聞き込みや過去の地盤状況と比較し、
現在の造成状況の影響を推測する事が可能です。現場観察は地盤調査の中でも
重要な役割があります。
調査では数字として示される換算N値に関心が集中しがちですが、
現場観察はとても重要な調査項目なのです。
特に現代の造成地盤では、既に造成が完了した状態での地盤調査が一般的です。
地盤調査では目視で確認できない敷地の状態や、数値として確認できない項目以外にも、建物の不同沈下の原因となる要因が有ることを理解しなければ建物の不同沈下は防げません。
<目視>する事、<予測>する事、そして<対策を講じる事>
これらは、建物の不同沈下を抑制する為には必要不可欠なのです。
- 小規模建物の不同沈下事故の原因の約80%に関わる<条件>
造成は、その<目的>と 造成後の<建物が受ける影響>が両方考慮されなければ
安全な造成とは言えません。
見かけが良くても、使用時の利便性を重視した造成でも、不同沈下の要因となる場合が
あります。
小規模建物の不同沈下事故の 原因の約80%は<造成に関係している>
と言われています。
例としては
● 擁壁に関係した造成の影響
● 傾斜地の盛土および切り土造成の影響
● 軟弱地盤への盛土造成の影響
などが挙げられます。
まず、上記項目が与える影響を考慮し建物の安全を確保する事が必要となります。
造成の形式や目的は多種多様で、一度で確認できる範囲を超えて造成される場合があり、その造成期間は2年以上の場合もあります。
造成規模は、数百棟規模の大規模な場合も有り、造成が行われた<規模>や<内容>を
掌握しづらい事もあります。
しかし、ほとんどの造成現場で確認することが出来る、造成に非常に関連の深い構造物があります。
それが <擁壁> です。
-
<擁壁>の目的と種類
擁壁を使用した造成は、大規模な宅地造成から一棟単位の造成まで様々です。
擁壁の種類も様々で、大きさや現地での造成の方法も多種多様です。
擁壁とは、がけ面の保護や崩壊を防止し擁壁背面に位置する地盤の安全を
確保する事が目的の構造体です。
その種類は大きく分けて2種類の構造形式に分類されます。
ひとつは 鉄筋コンクリート造のL型やT型と総称される物
もうひとつは練積み構造の間知石積み等の形式になります。
間地石積み擁壁の形式は、地面の勾配に積み重ねてゆく形式の為
宅地造成等規制法や都道府県や市町村の詳細な規定が設けられています。
鉄筋コンクリート造擁壁は、高さ規定は無く構造計算で安全を確保しています。
主に戸建ての住宅の造成で問題となりやすいのは、鉄筋コンクリート造擁壁です
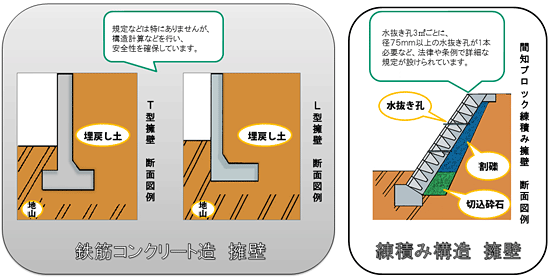
- 擁壁造成された敷地と 建築される建物の関係性
建物を建てる事を目的とした宅地を造成する際、
現在の土地の活用状況から、全く造成を行わず建物を建てる事が出来る場合は限られ、
ほとんどの場合は造成により整地した状態となります。
この時、隣地との高低差等に応じた擁壁造成が行われます。
しかし、擁壁造成時点で建物の計画が明確な場合は殆ど無く、建物配置も
確定した状態では無い場合が殆どです。
擁壁の設計では、地表面に上載荷重を見込んだ設計が行われる事になり
実際に建築された建物や、建物配置が擁壁に対して与える影響を慎重に検討する必要が
あります。
当然 擁壁の安全許容範囲が不明瞭な場合や、安全を維持する事が出来ない場合は
擁壁に負荷となる建物建築は、擁壁自体の不同沈下やそれに付随した
建物の不同沈下の要因と成る事が懸念される状態となります。
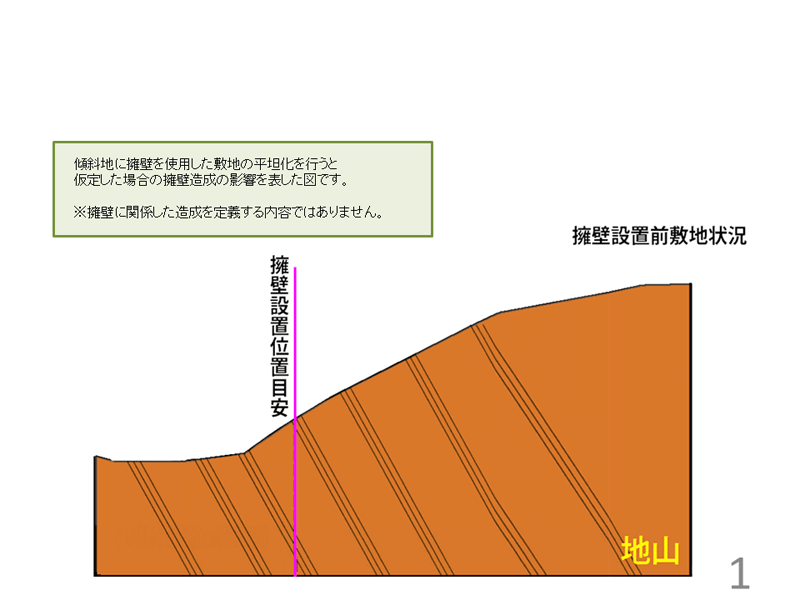 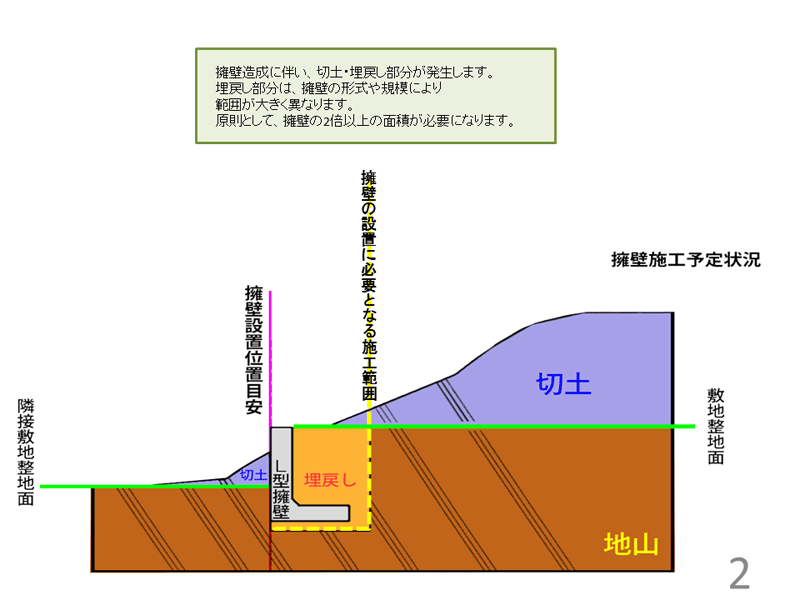 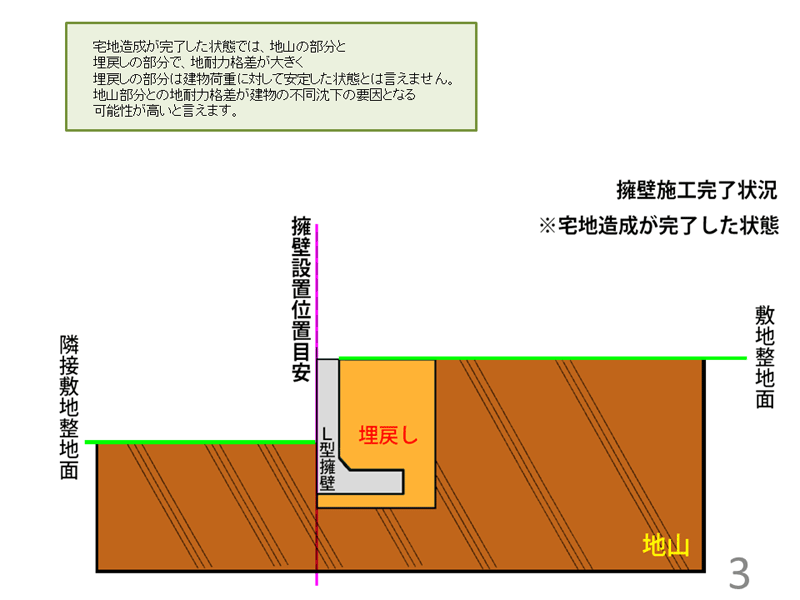
※クリックすると拡大します。
- 擁壁に見られる異常とは
擁壁の設計で確認されるべき内容は、
<転倒や滑倒> <支持力> <背面土のすべり>
の、安全を確認する必要があります。
近年の擁壁の不具合は、地震の影響も含め上記3項目の
安全を確保する事が出来ていない擁壁に集中する傾向があります。
不具合が確認された擁壁には、共通した特徴が見られます。
代表的な特徴として
● 水抜き孔が無い または 正常に機能していない
● 空石積み擁壁
● 二段またはそれ以上の近接した擁壁
● 異種材質および異種構造体等を使用した増積み擁壁
● 擁壁下部地盤の支持力不足 または 支持力未確認地盤への擁壁の接地
● 造成時期の異なる増積み擁壁
上記内容が 複数当てはまる場合、問題が同時又は時間を置いて確認された場合など
さまざまなケースがあります。
- 擁壁に異常が見られなくても不同沈下は発生します
擁壁が破損し、土壌が流失するような事態が起きなくても
擁壁の造成の影響は建物の不同沈下の原因となりえます。
<L型擁壁>や<T型擁壁>を使用した擁壁造成に多く見られ
擁壁の高さが1.00m〜2.00m程度の比較的小規模な擁壁に関係して発生する事例が
多く確認されています。
これは、擁壁の構造とその設置工事の内容に起因する場合が多くあります。
擁壁を設置する為の、埋戻しを伴う施工範囲と擁壁造成に関係無い部分との
地耐力格差および沈下量の格差から発生する建物の不同沈下です。
本来擁壁から建物の距離は、安息角に応じた距離を確保する事が必要とされます。
しかし実際は、敷地内での建物位置は擁壁の影響範囲を考慮するよりも
生活環境や敷地の建築効率を優先する場合が多く、擁壁造成の影響範囲内や安息角に
応じた擁壁からの距離は確保されない場合があり対策が必要となります。
- 支持力不足の地盤や盛土による造成地盤に設置された擁壁について
擁壁の造成による影響範囲は、比較的大きく
その影響範囲を避けて、敷地に建物を建築する事は
建物配置に大きな制約を設ける場合があります。
擁壁に近接する場合は造成の影響を考慮した対策が必要となります。
また擁壁下部地盤の支持力不足や、不均等な支持地盤に構築された擁壁は当然安定した状態を保つことはできません。
傾きや回転・沈下等により建物の不同沈下の要因となります。
必要とされる地耐力を考慮して設計されるべき擁壁が、敷地の平坦化と敷地の有効利用の為に <土留め>として使用される場合でも、建物はその影響範囲内を充分に考慮する事が必要です。
支持地盤として盛土に直接接地された擁壁は、盛土の経年変化に伴い不安定な状態になる事が安易に想像できます。
盛土は、その造成方法や造成時期、使用されて盛土材等に応じて
安定するには一定の期間が必要となります。
盛土に瓦礫等の混入物が確認された場合は、
混入物の大きさや質量により造成時期に関係無く、
安全を確保する為にかかる時間は長期となり、その間敷地を放置する事になります。
擁壁下部地盤が盛土や造成地盤の場合は、擁壁に対する地盤対策が必要となり
その対策には、予測される建物荷重も考慮する事が必要となります。
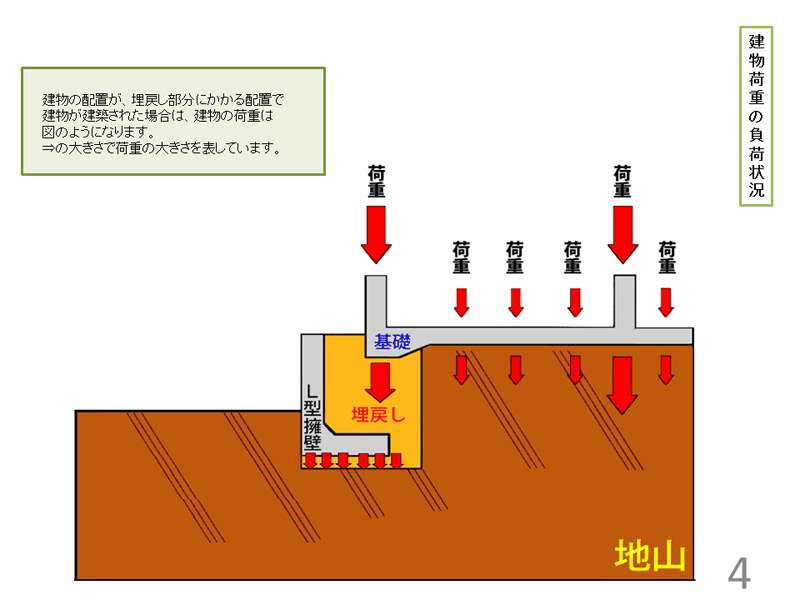 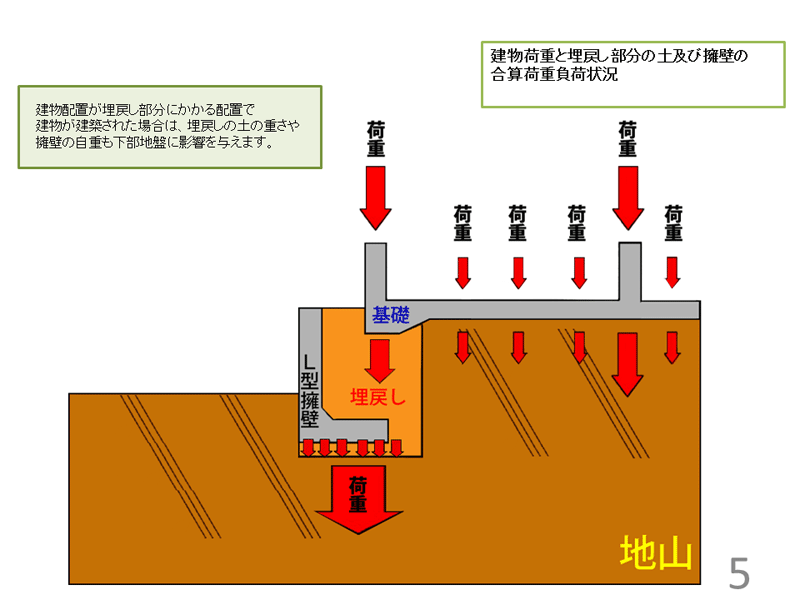 
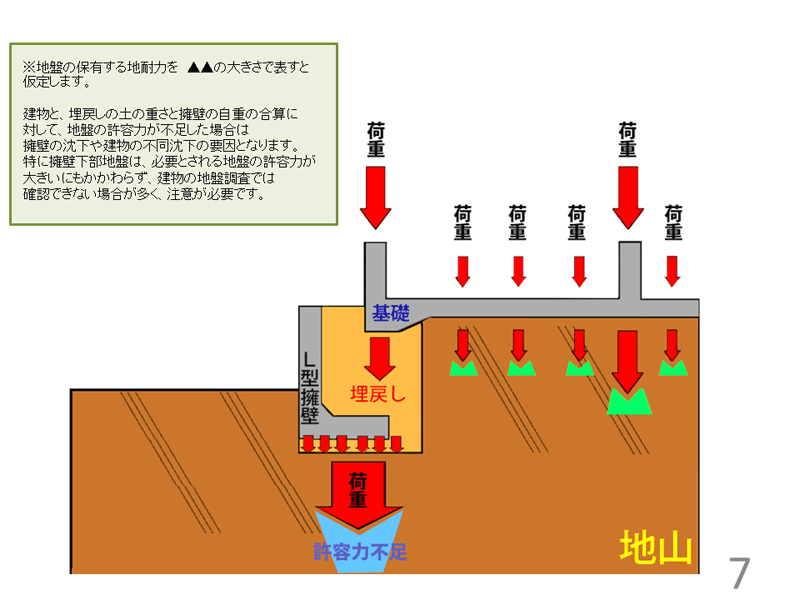  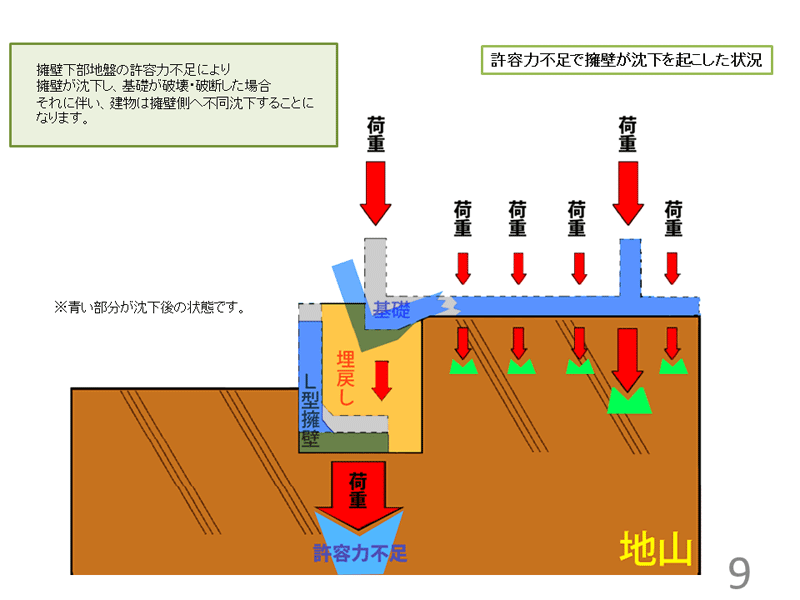
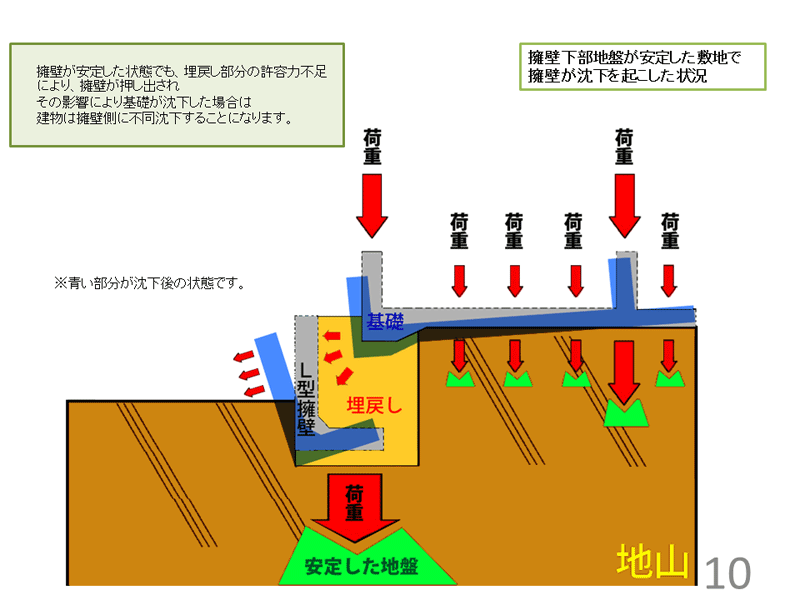 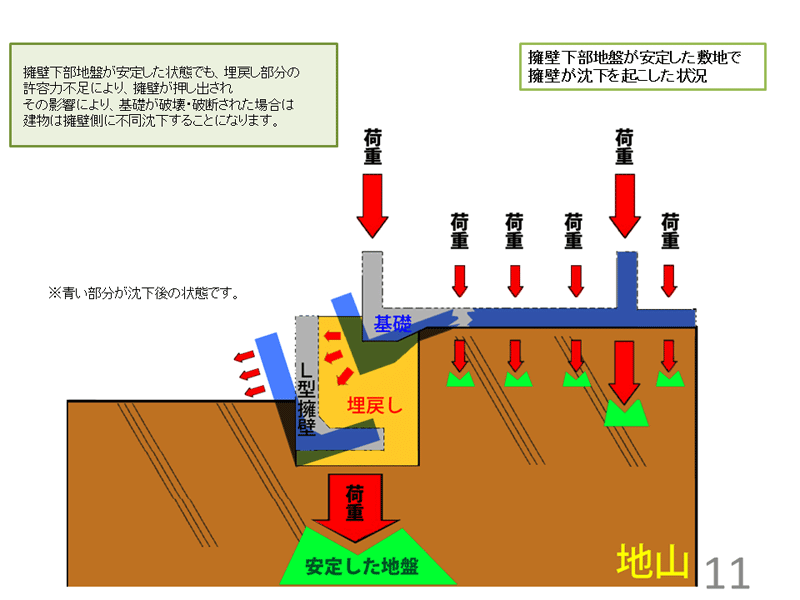
※クリックすると拡大します。
- 擁壁のある敷地は 擁壁に関係した対策が必要です
擁壁を使用した整地は、敷地の有効活用に際し費用効果が高く
敷地の平坦化や隣地の高低差に対する整地にも有効です。
擁壁に関係した<不同沈下>の危険性は
建物と同様に、<事前調査>から安全を見越した設計を行い、
必要とされる地盤対策を行う事で、排除することが可能です。
しかし、それに伴う<費用>や<時間> の問題
そして、「通常はやらない」「たぶん大丈夫」等の根拠の曖昧な<経験値>が優先されがちです。
地盤調査とは、現状敷地状況から考えられる危険性を検知し、その内容を検討し
有効な対策を提案する為にあります。
建物と同様に<擁壁>にも必要とされる
<調査・設計・施工>が有る事を考慮した上で、現場観察から擁壁に関係した危険性を
検知する事が重要となります。
- 擁壁が関係した敷地なら 調査・検討は必要です
地盤調査は、その内容から 予定される建物に対する地盤の状態を掌握し
地盤に対する建物の設計の基礎と成るべき様々なデータを計測、または観測する事が目的です。
しかし、今回のテーマである<擁壁>の影響は、地盤調査では完全に掌握する事が
極めて困難だと言えます。
擁壁の構造上の特徴を理解し、擁壁が敷地や建物に与える影響を考慮し
その造成状況を<予測>し、影響を考慮する事で建物の安全を確保する為の有効な対策を行う事が重要になってきます。
明確な数値として、調査報告書には表記されない内容であっても
建物に与える影響を考慮する事は重要です。
擁壁が対象の敷地に確認された場合は、擁壁に関係した調査・検討は必要なものだと考えます。
|
 |
|
|

